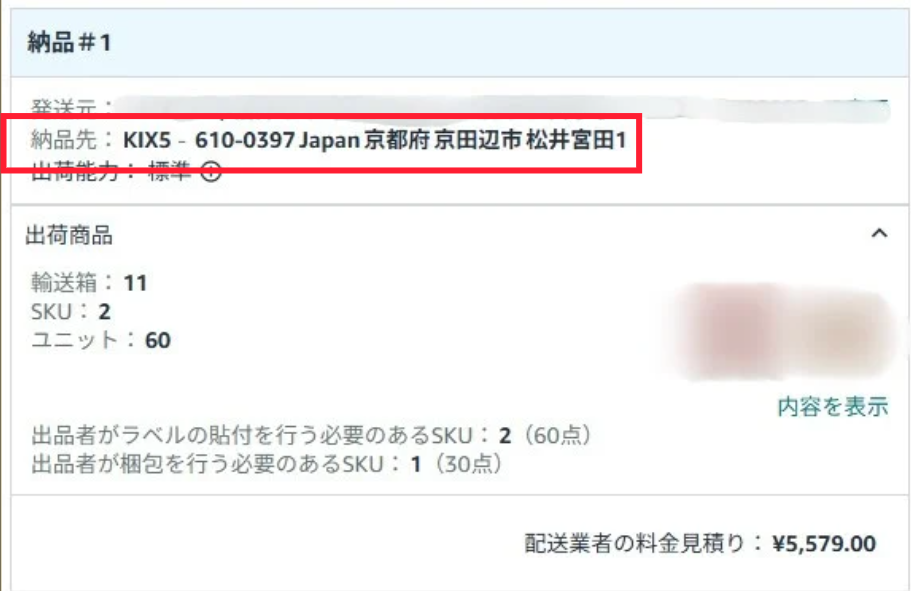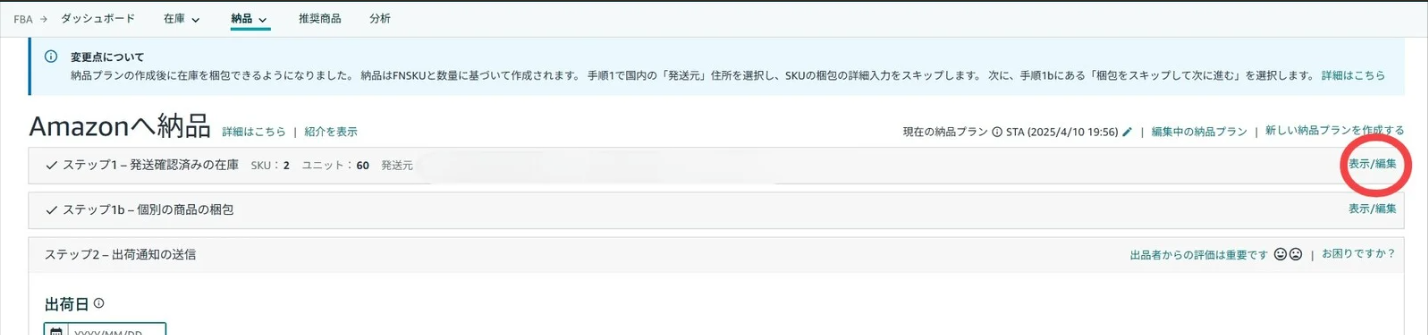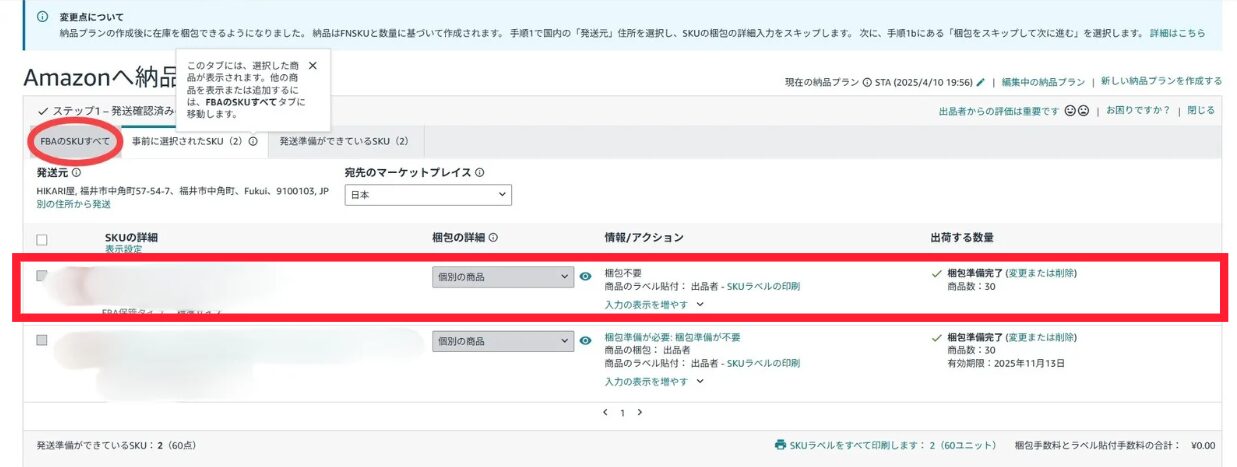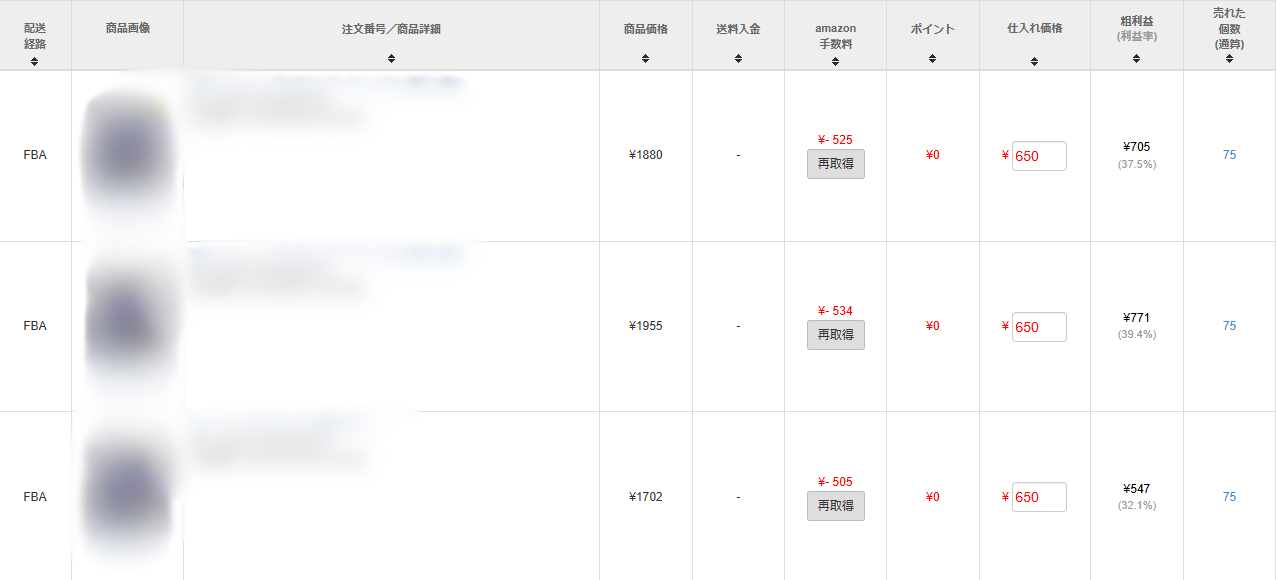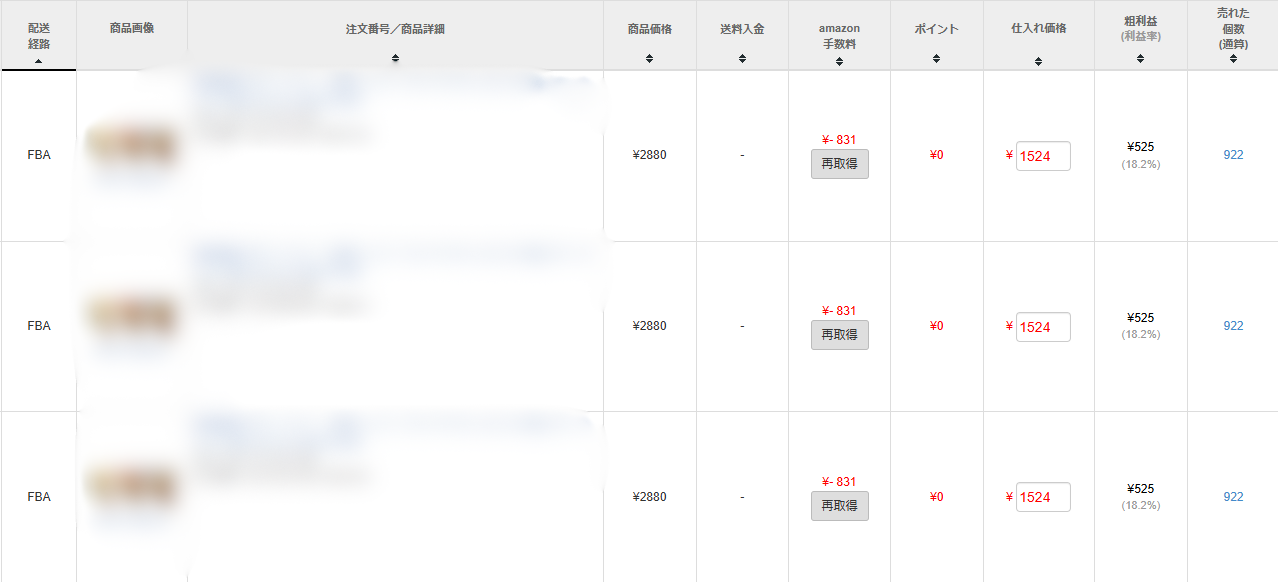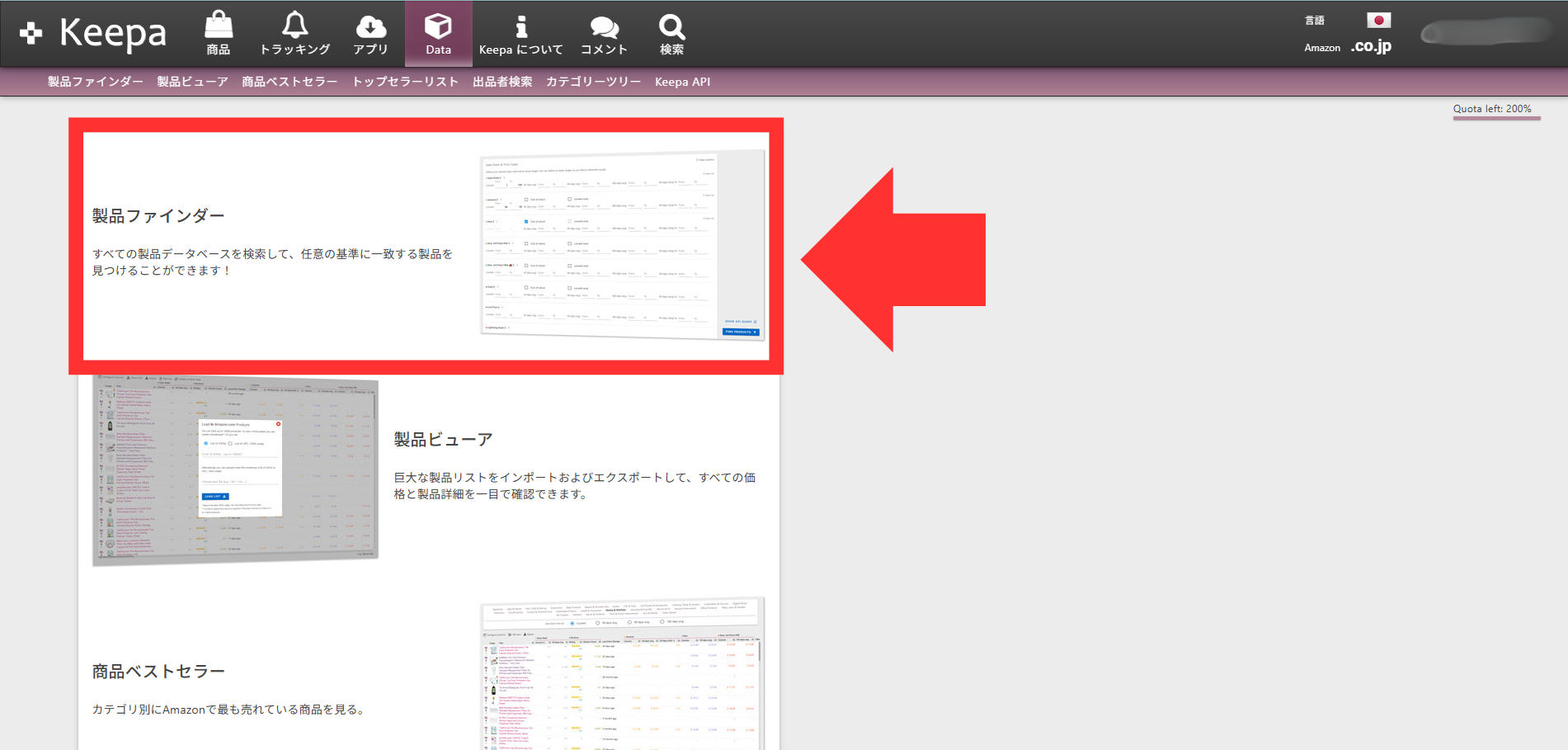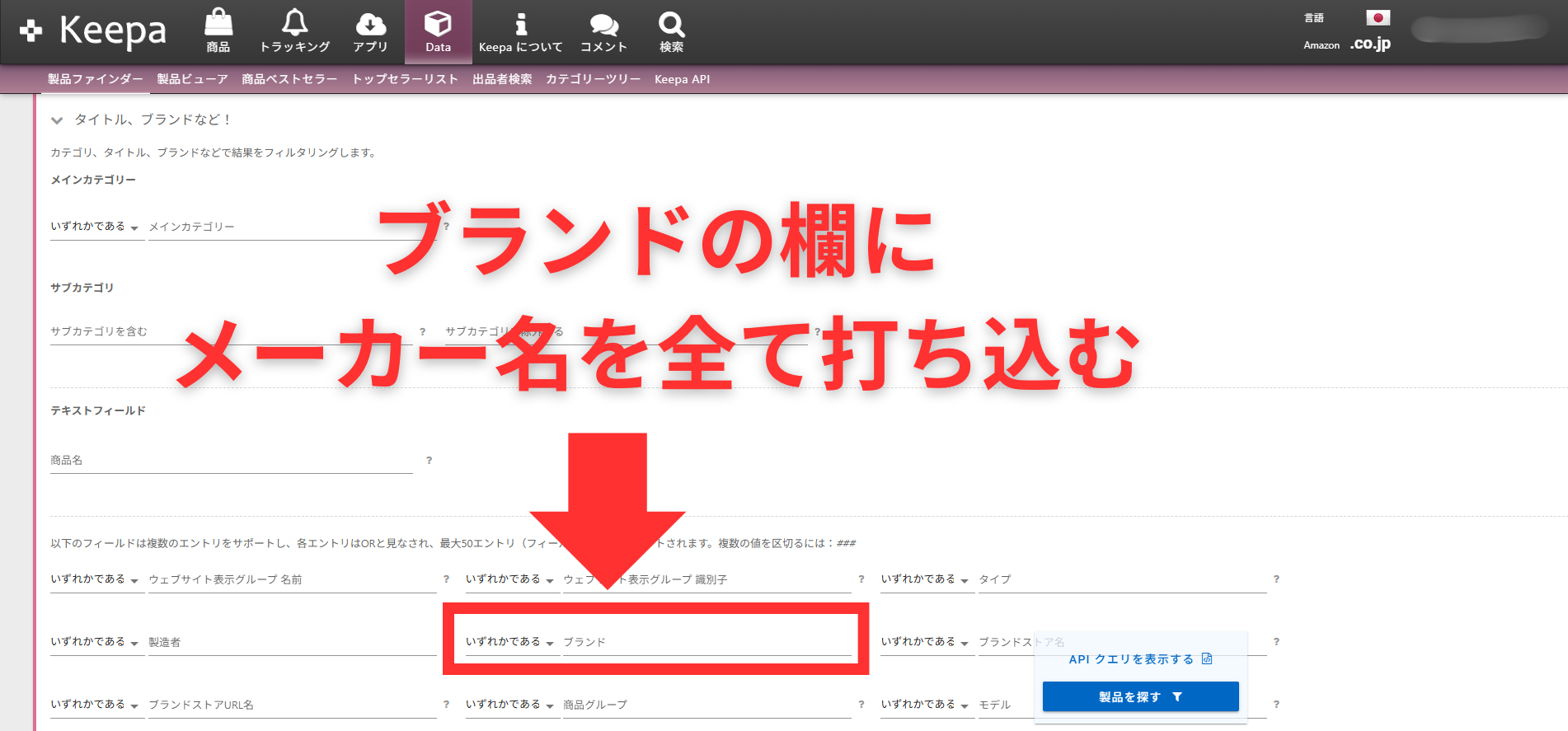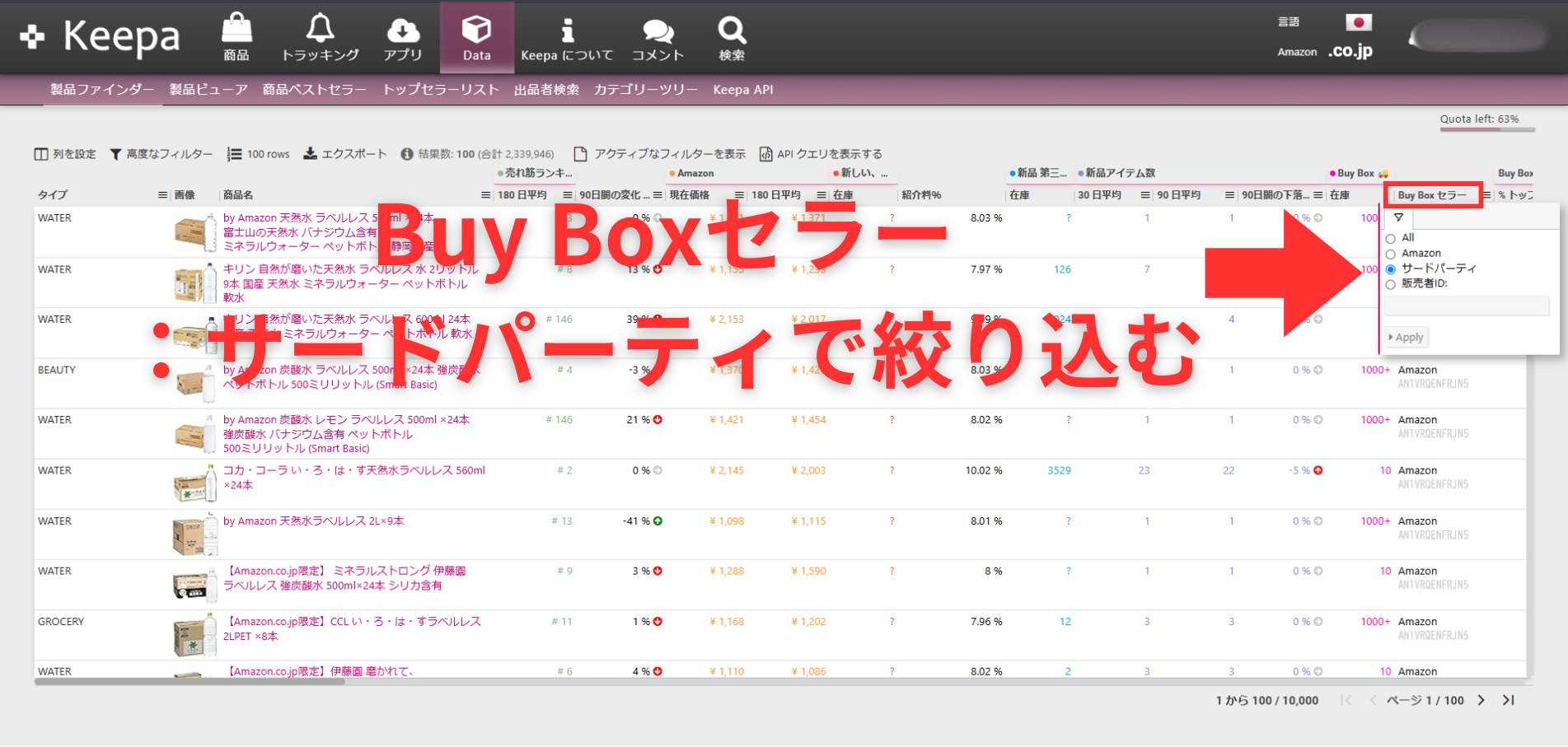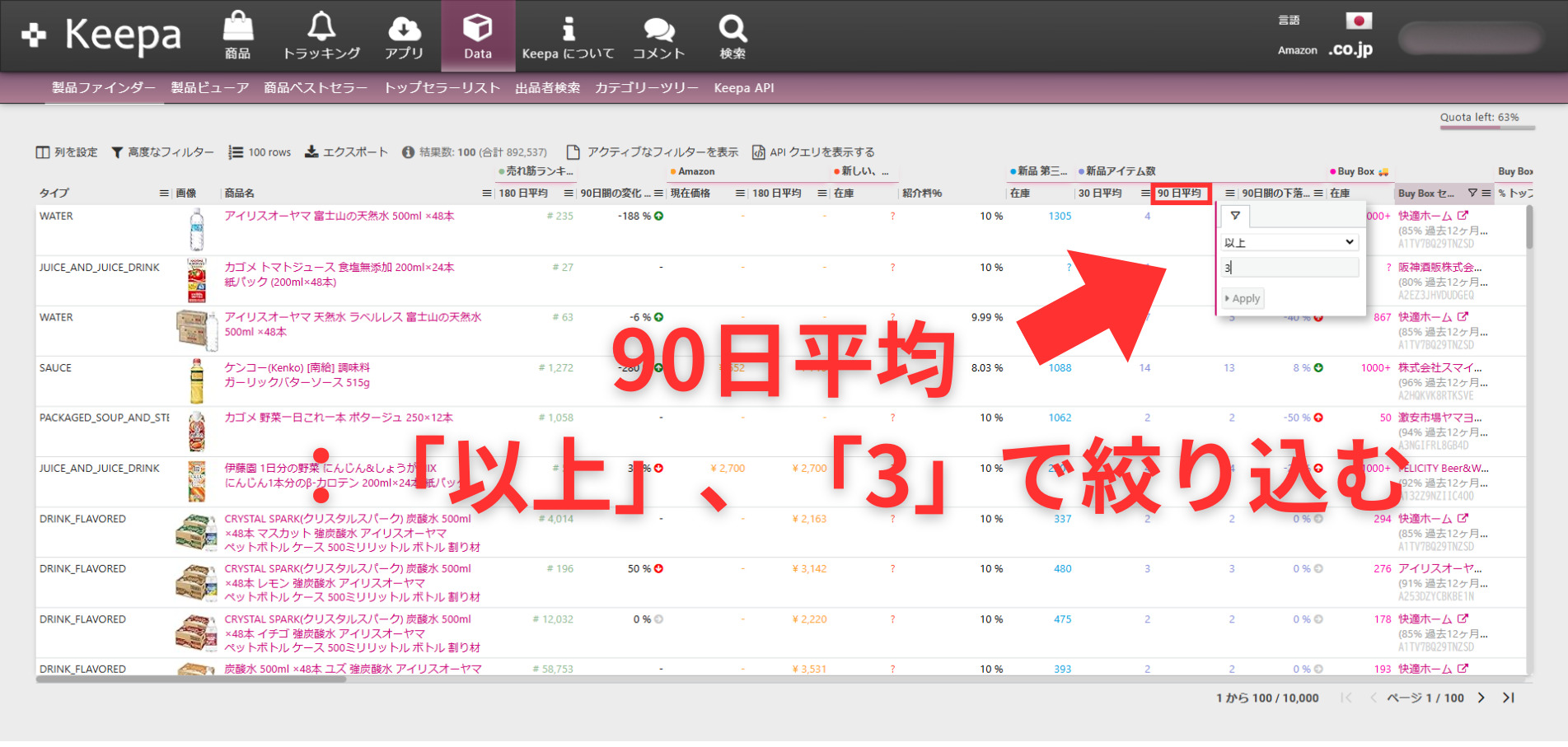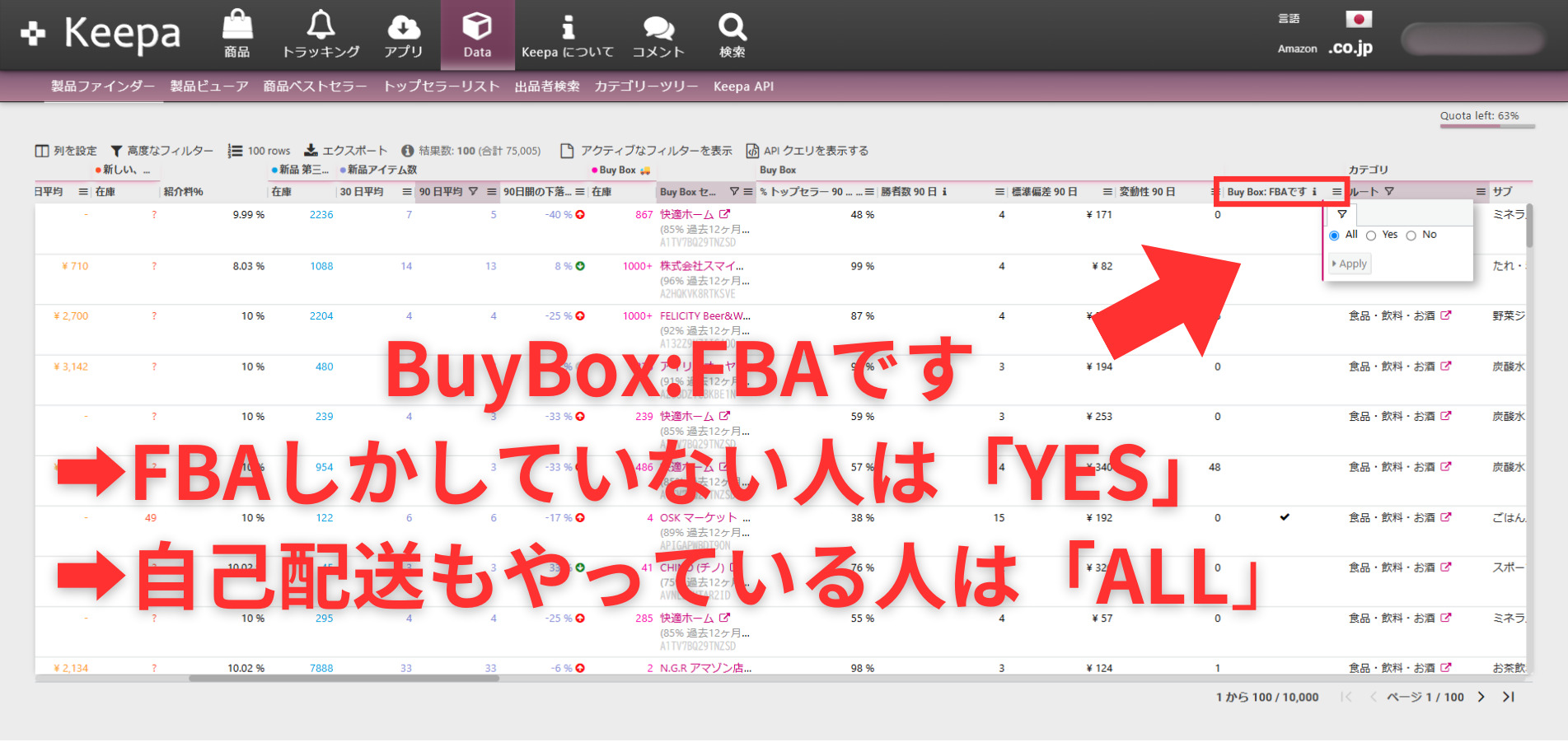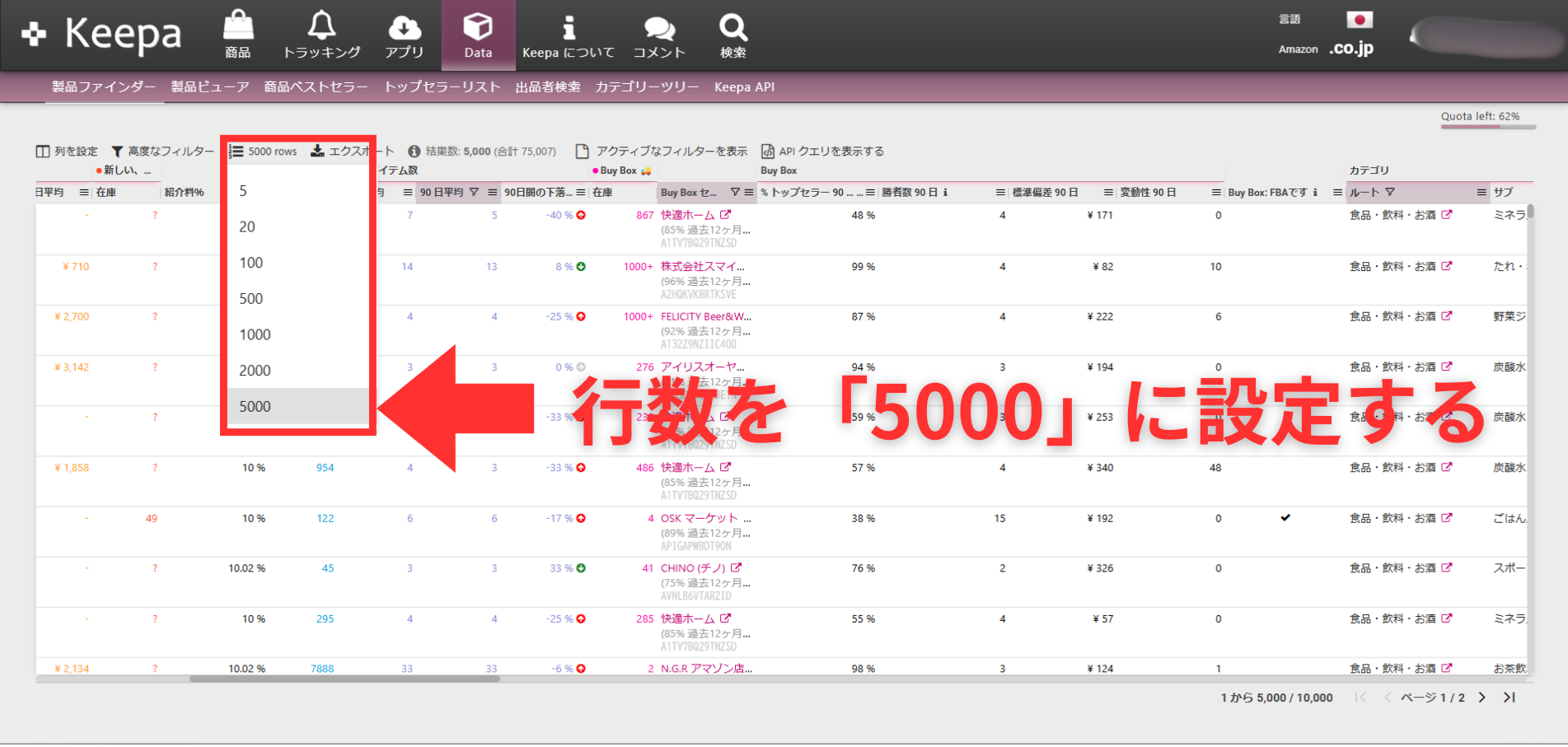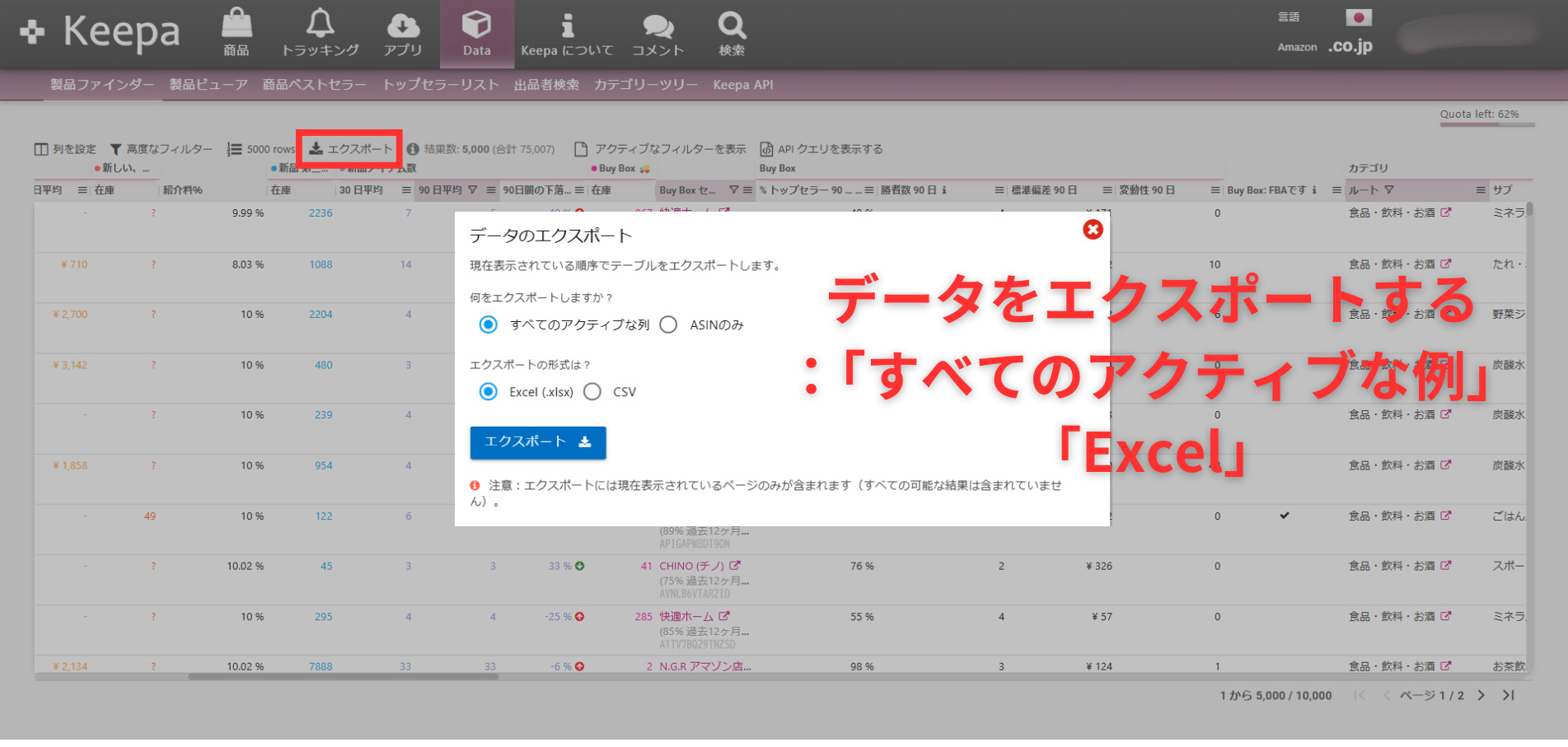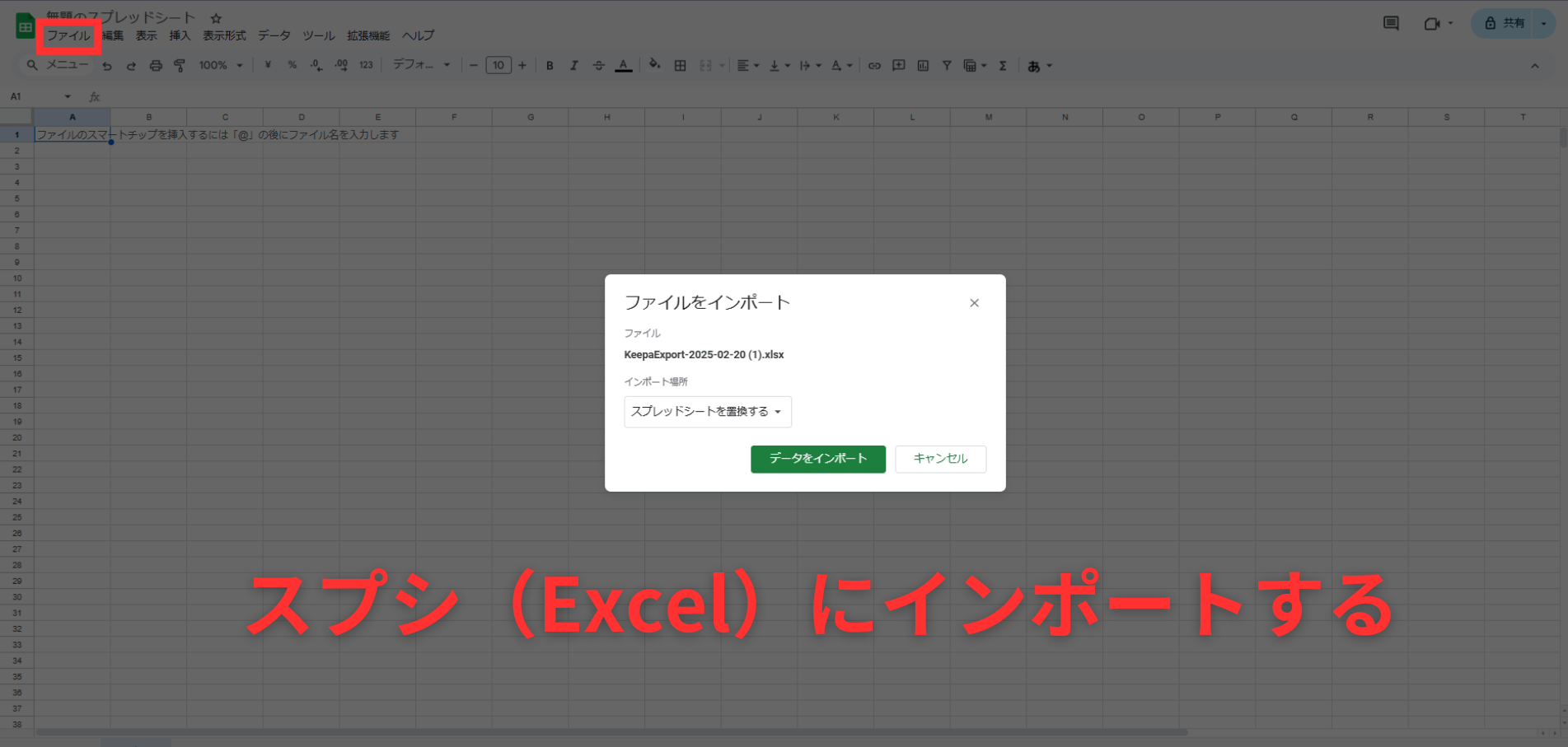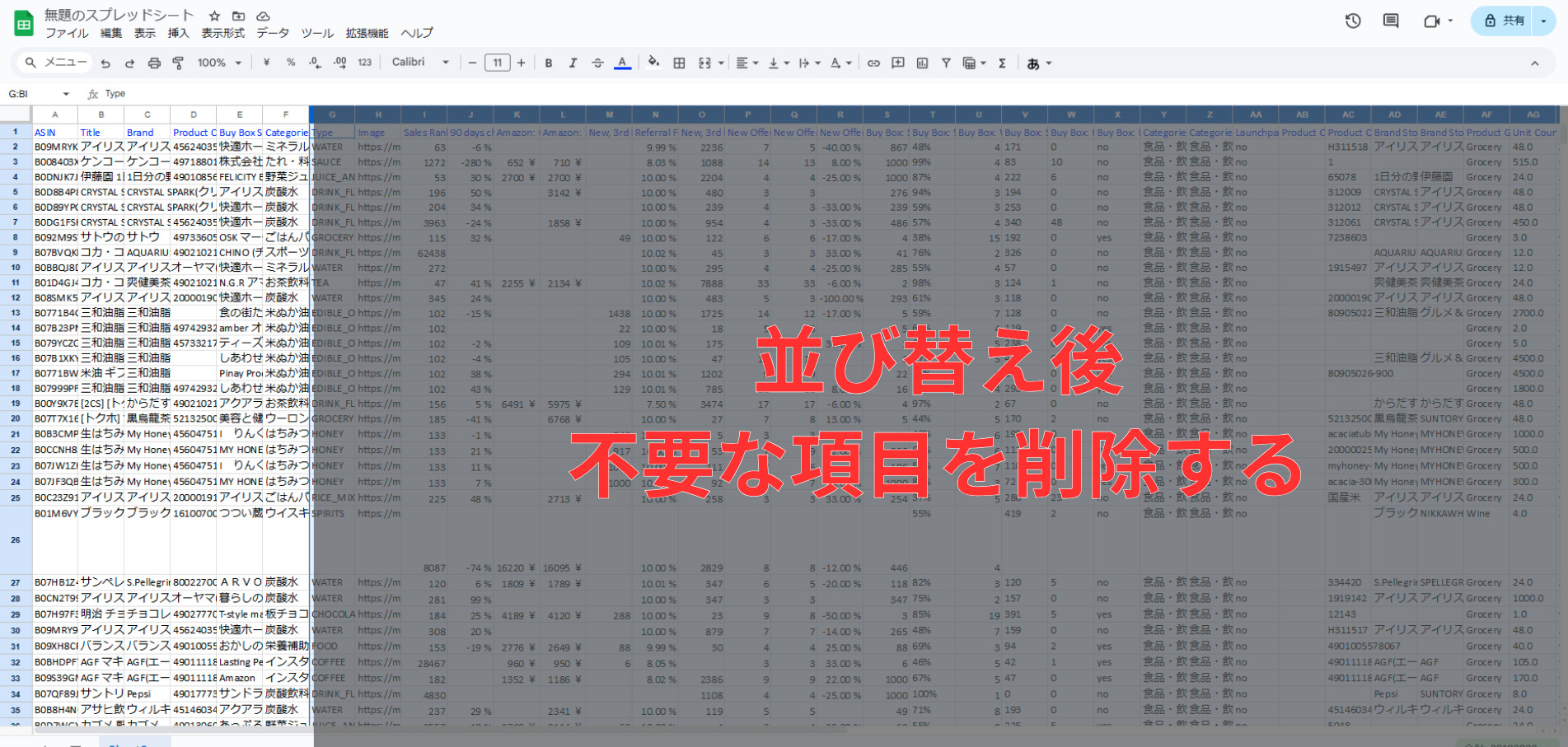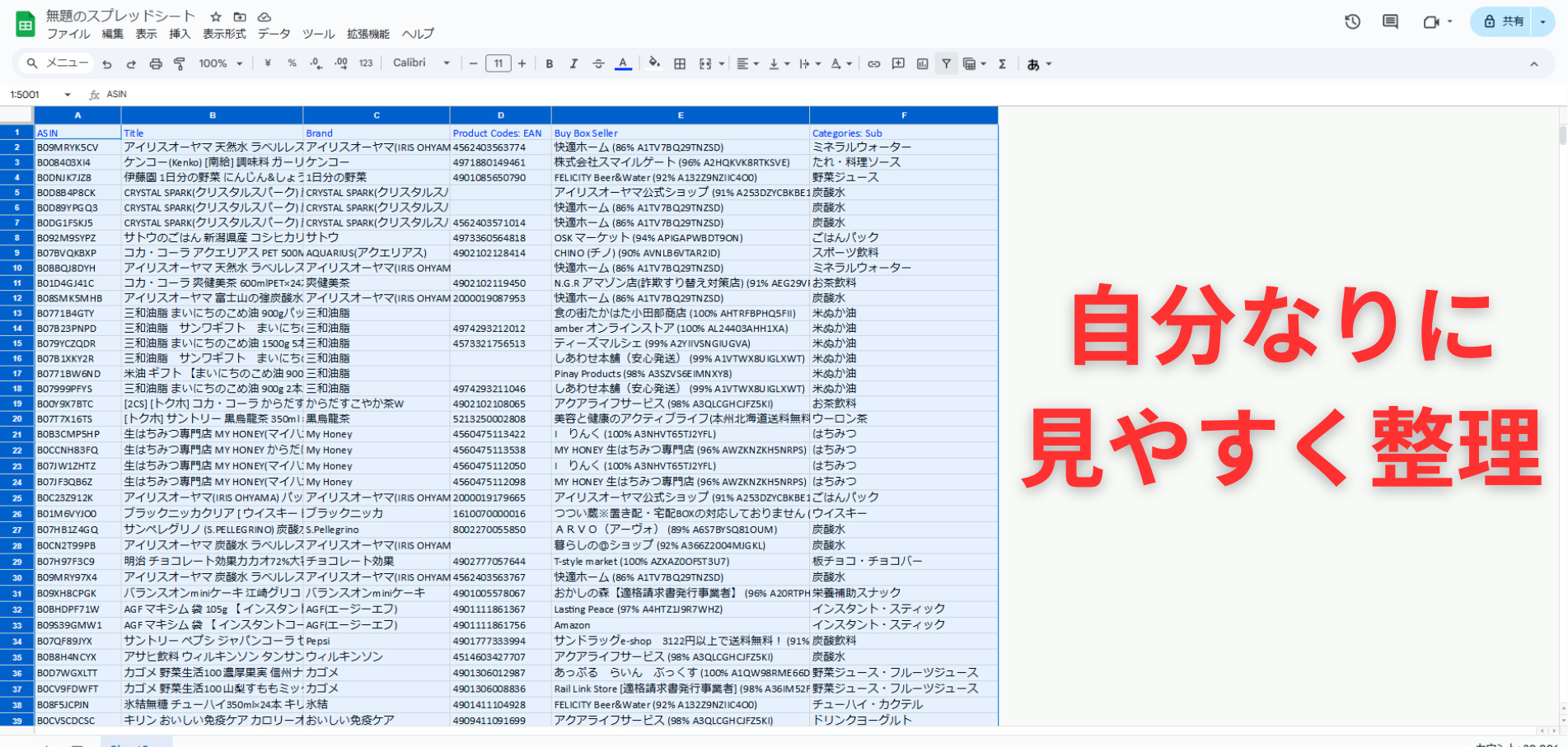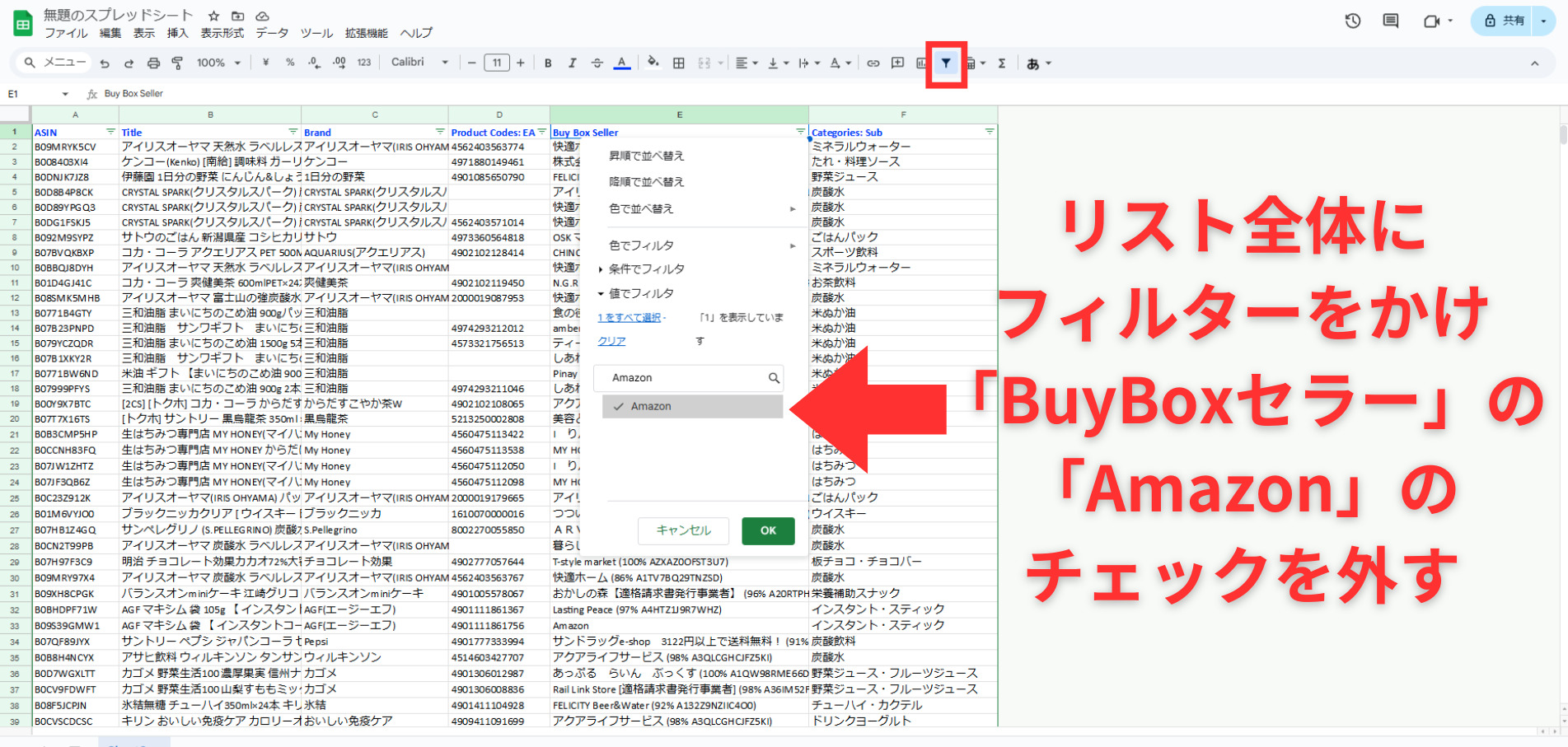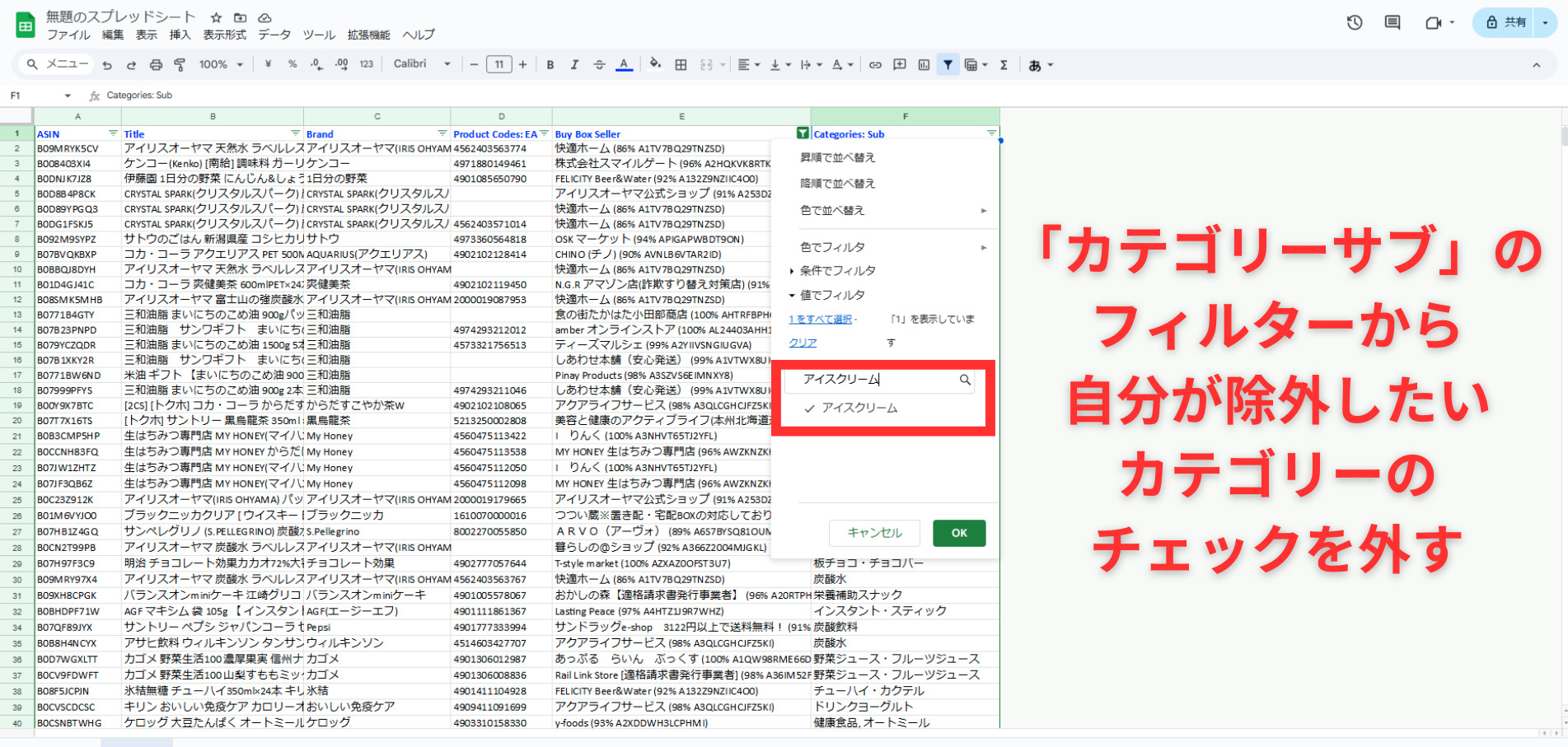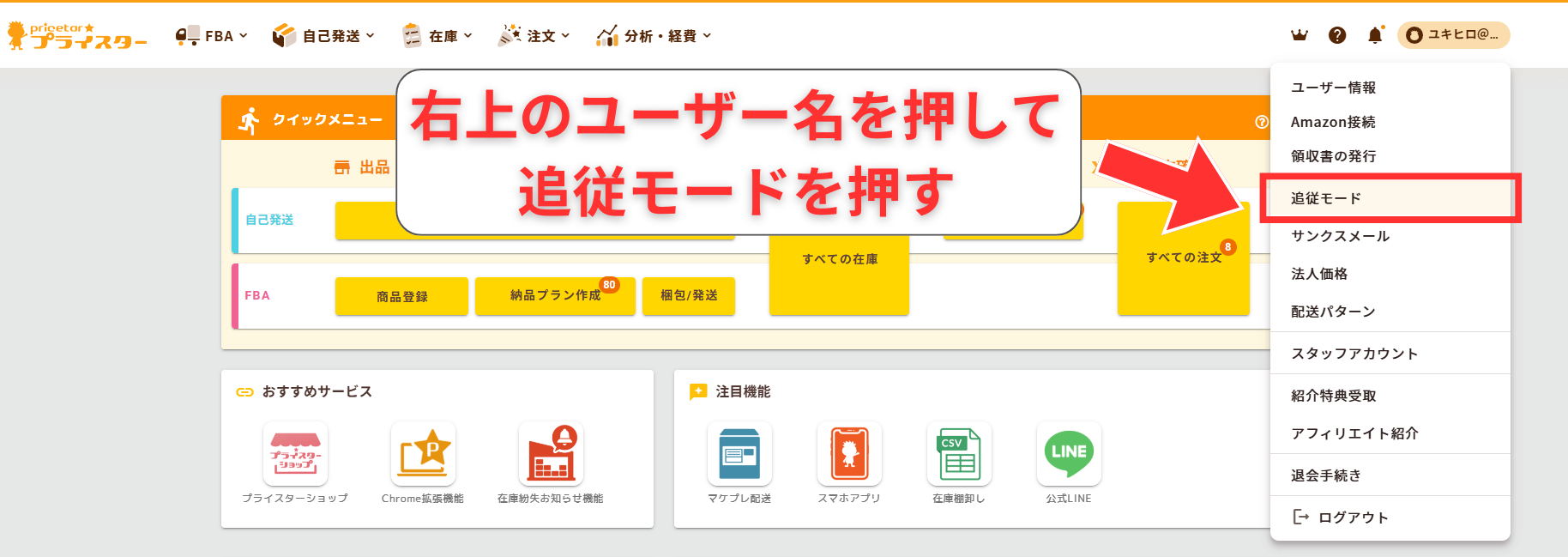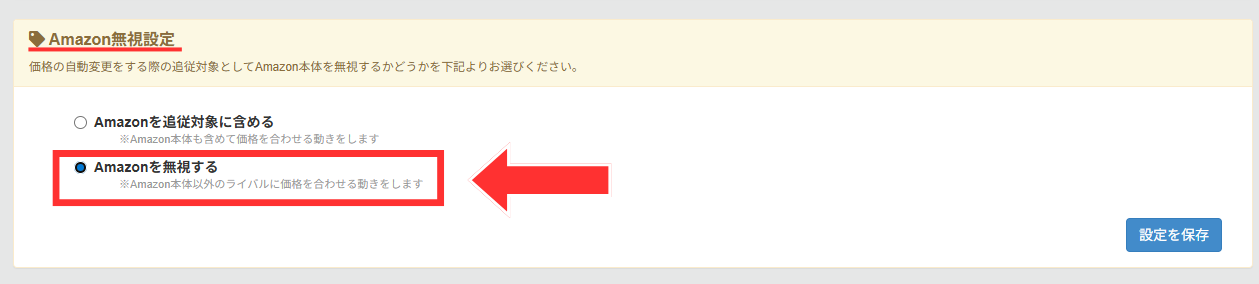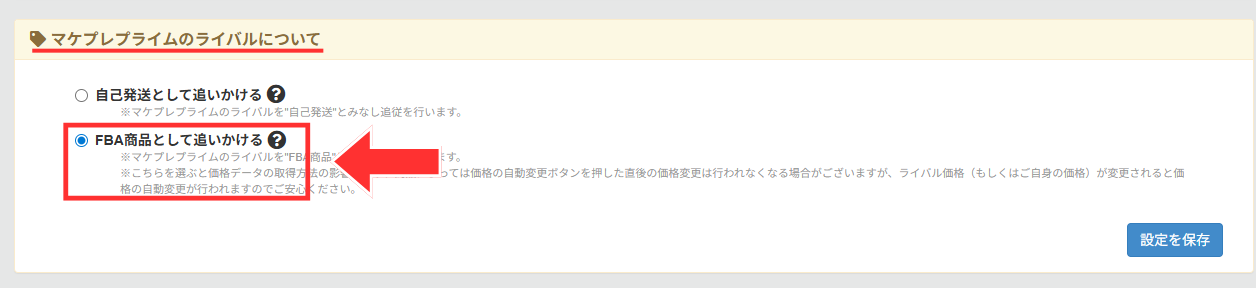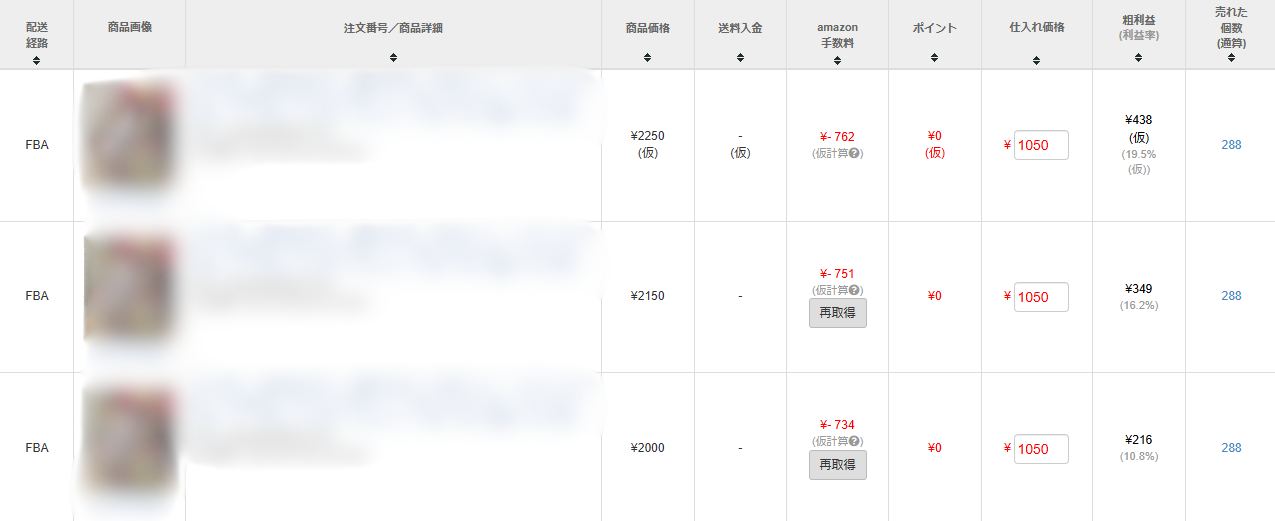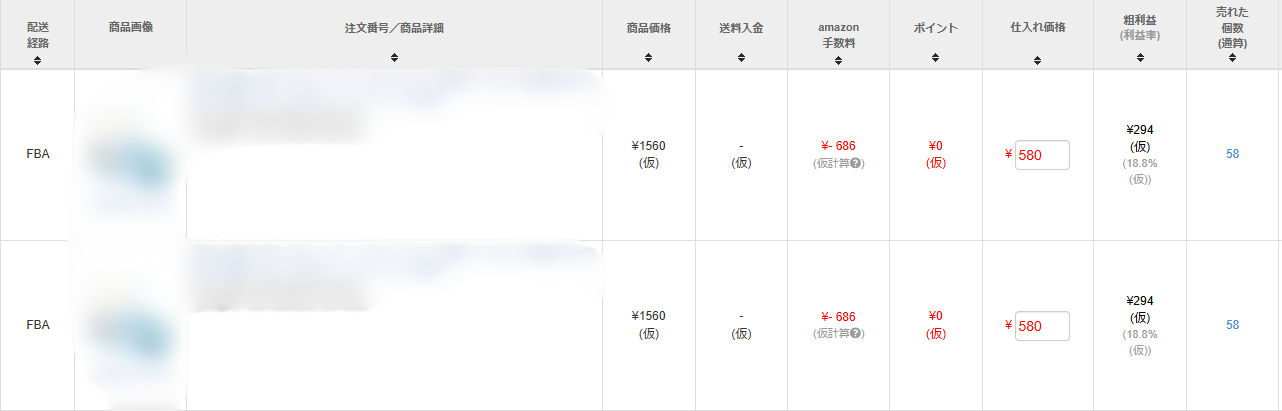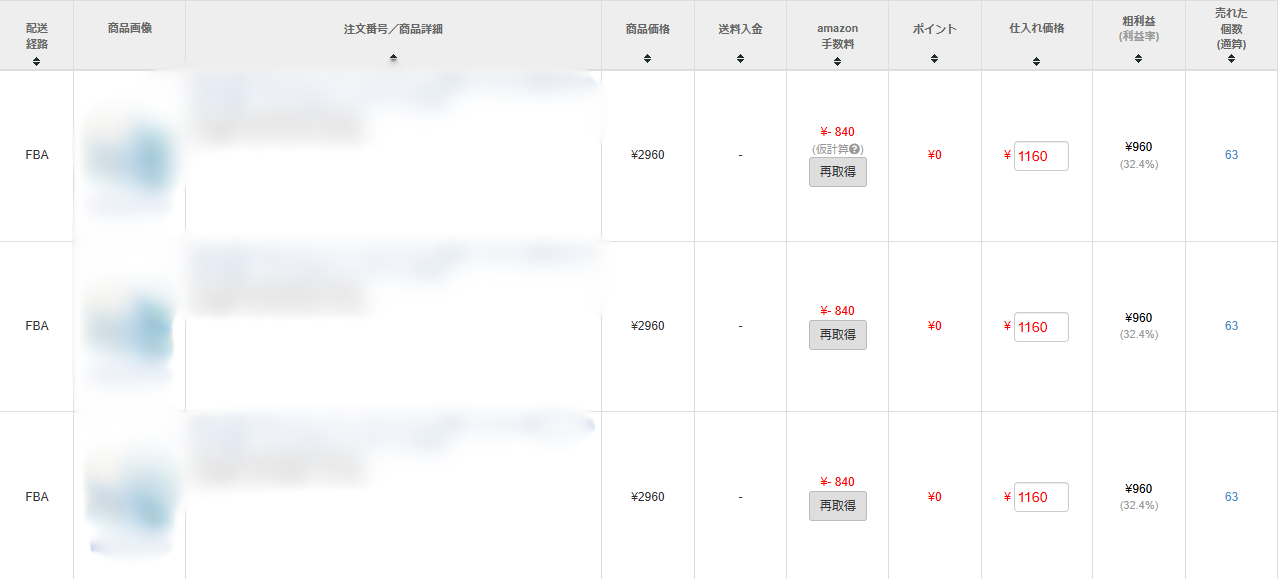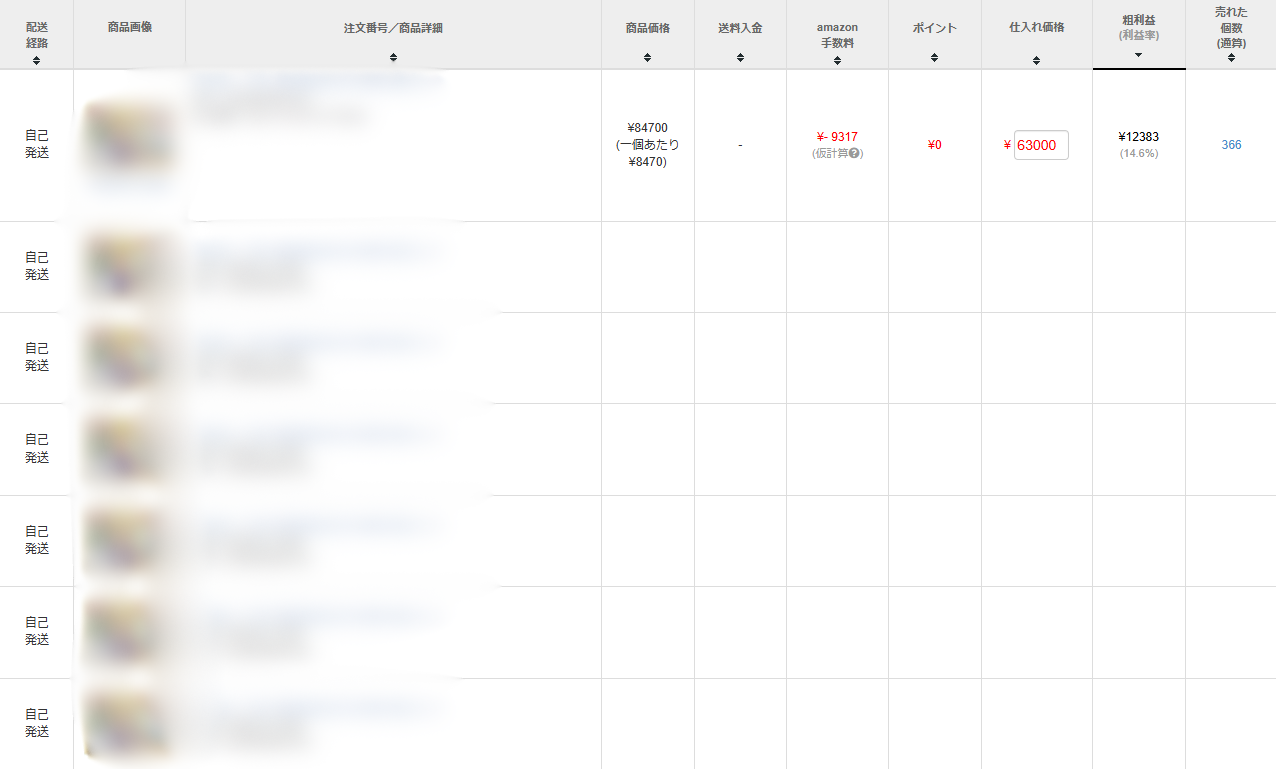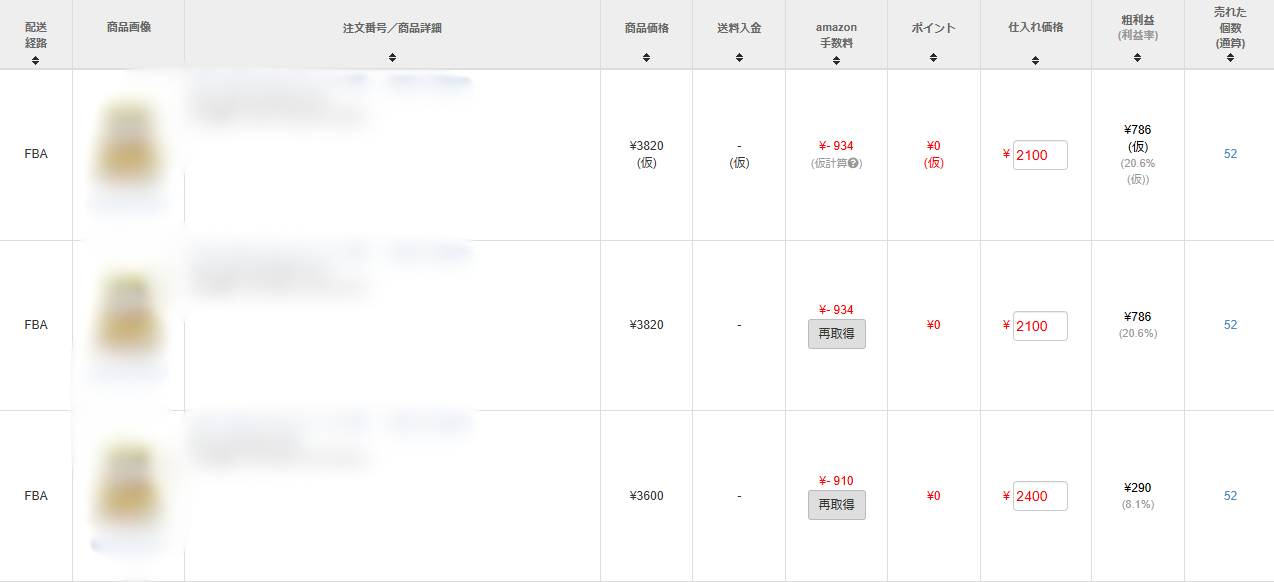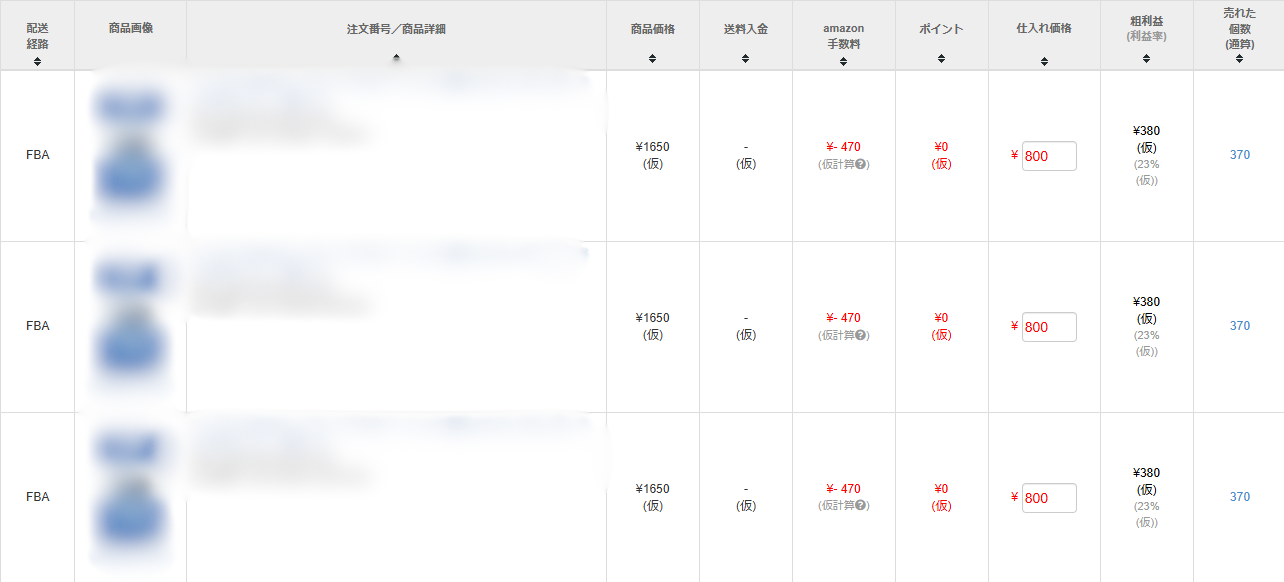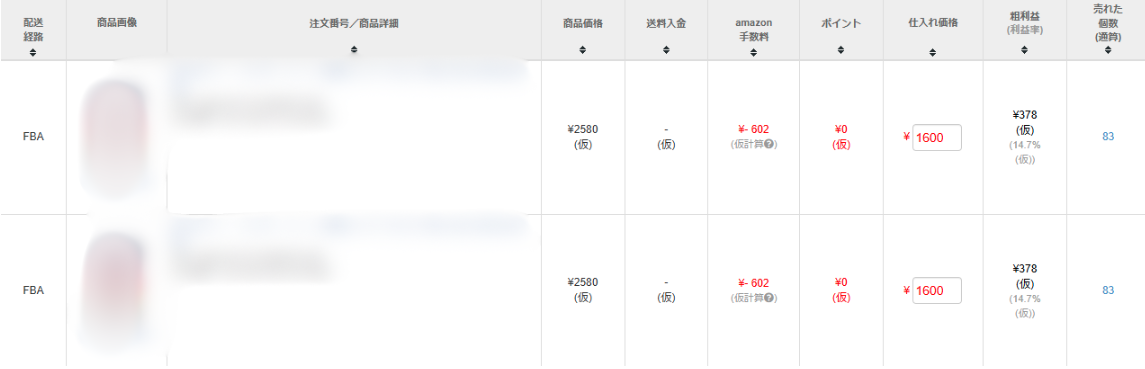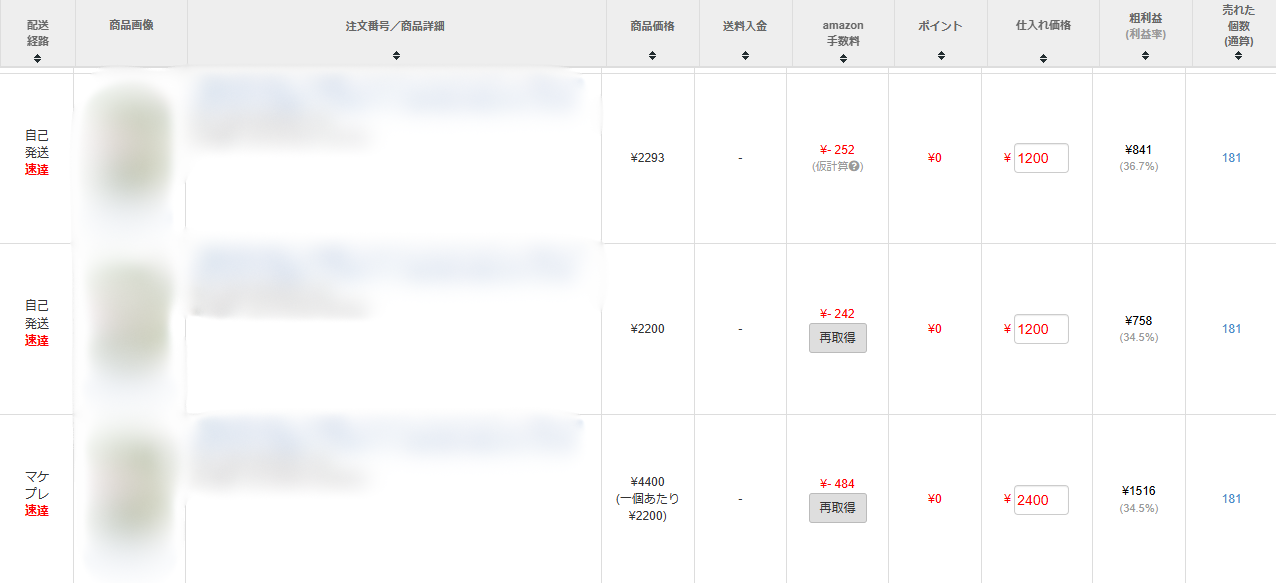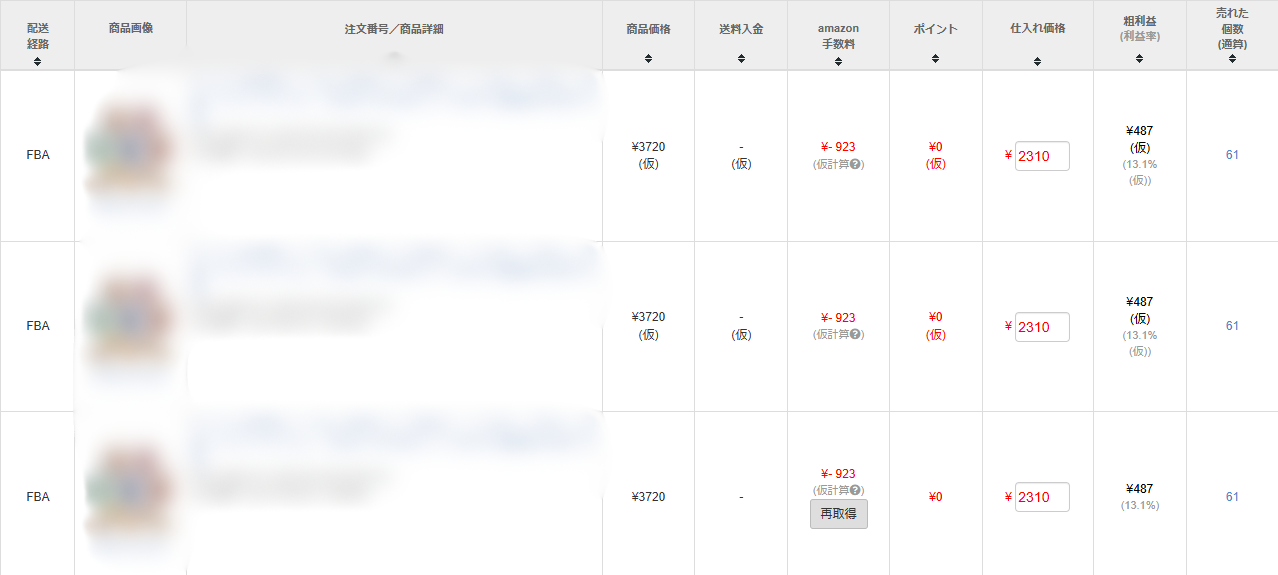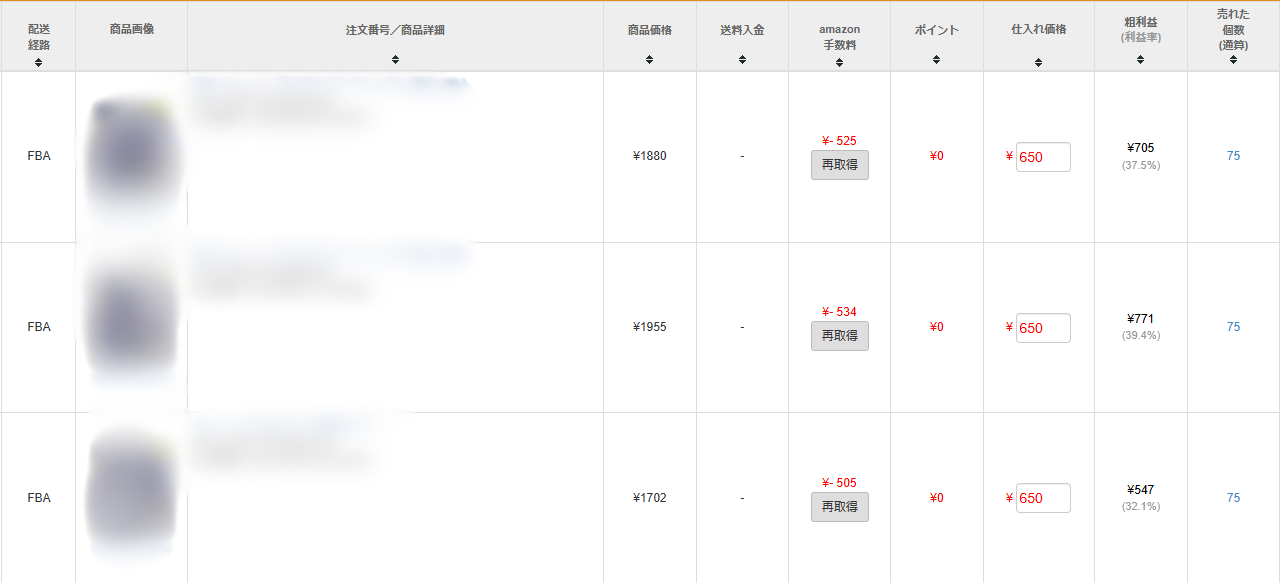はじめに
ご覧いただきありがとうございます!
結論から申しますが、
プライスターで情報を一括で変更するためには「CSVファイル」を活用します。
一つずつ価格改定とかをするのはかなりの時間の無駄になるので、
ぜひ今から解説する方法を使ってみてくださいね!
一括変更方法
下記のステップに沿って設定を行ってください。
ステップ①
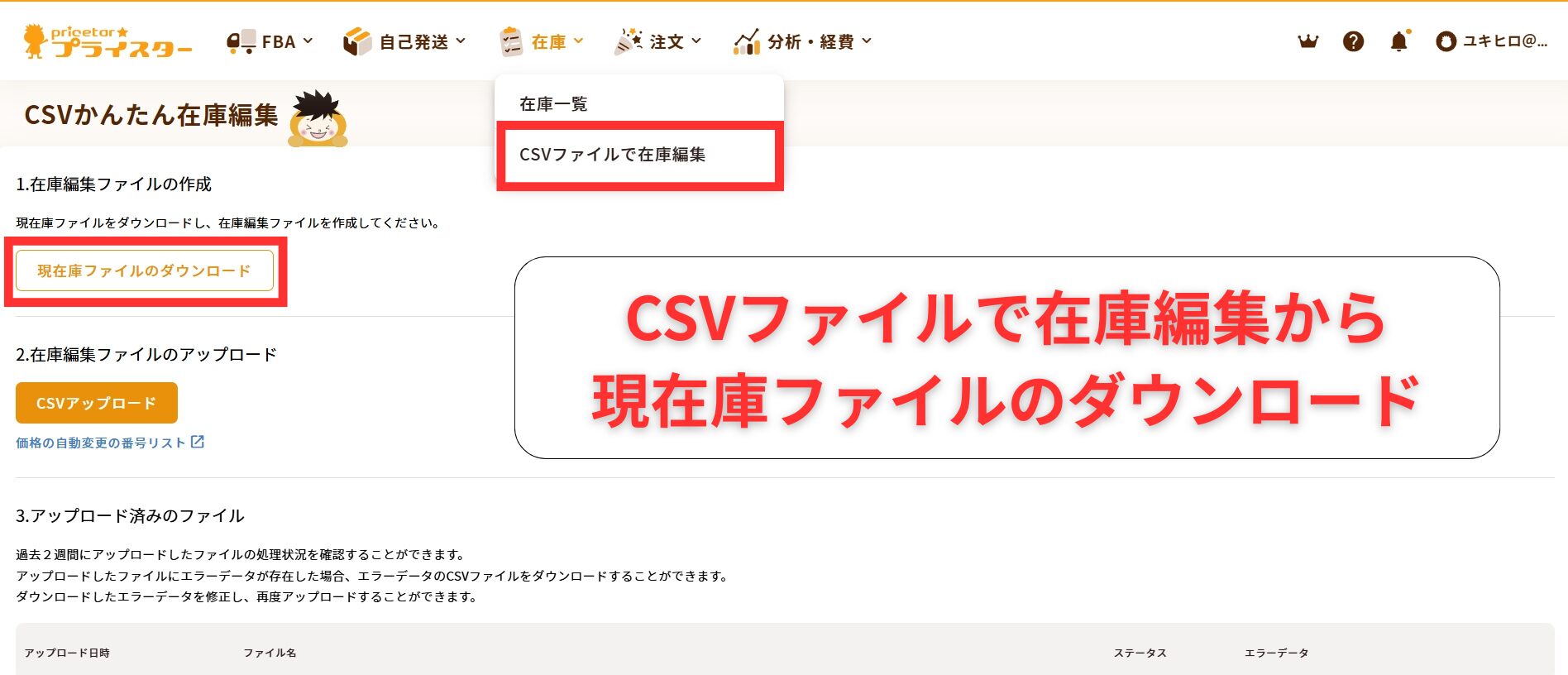
「在庫」のタブから「CSVファイルで在庫編集」を選択して、
「現在庫ファイルのダウンロード」を押す。
ステップ②
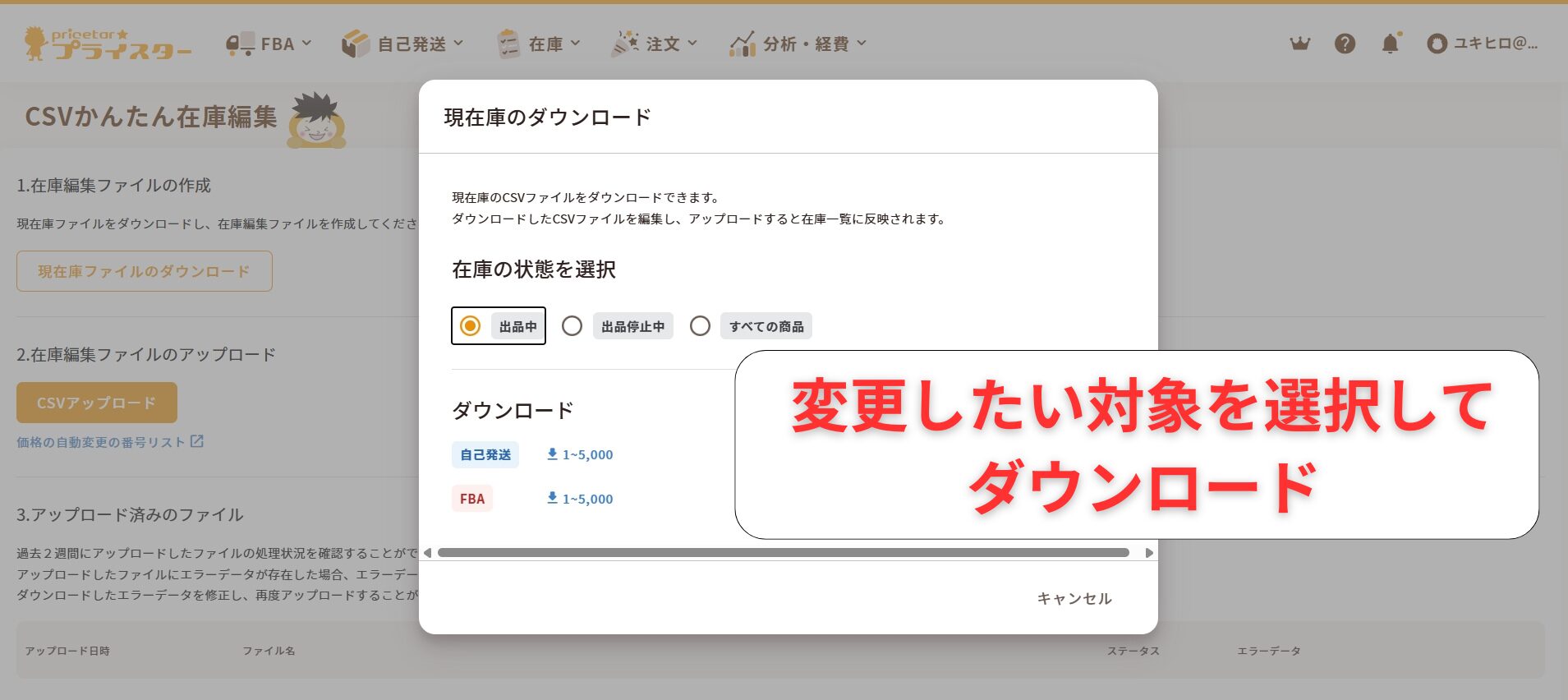
一括で情報を変更したい対象の条件を選択して、ファイルをダウンロードする。
ステップ③
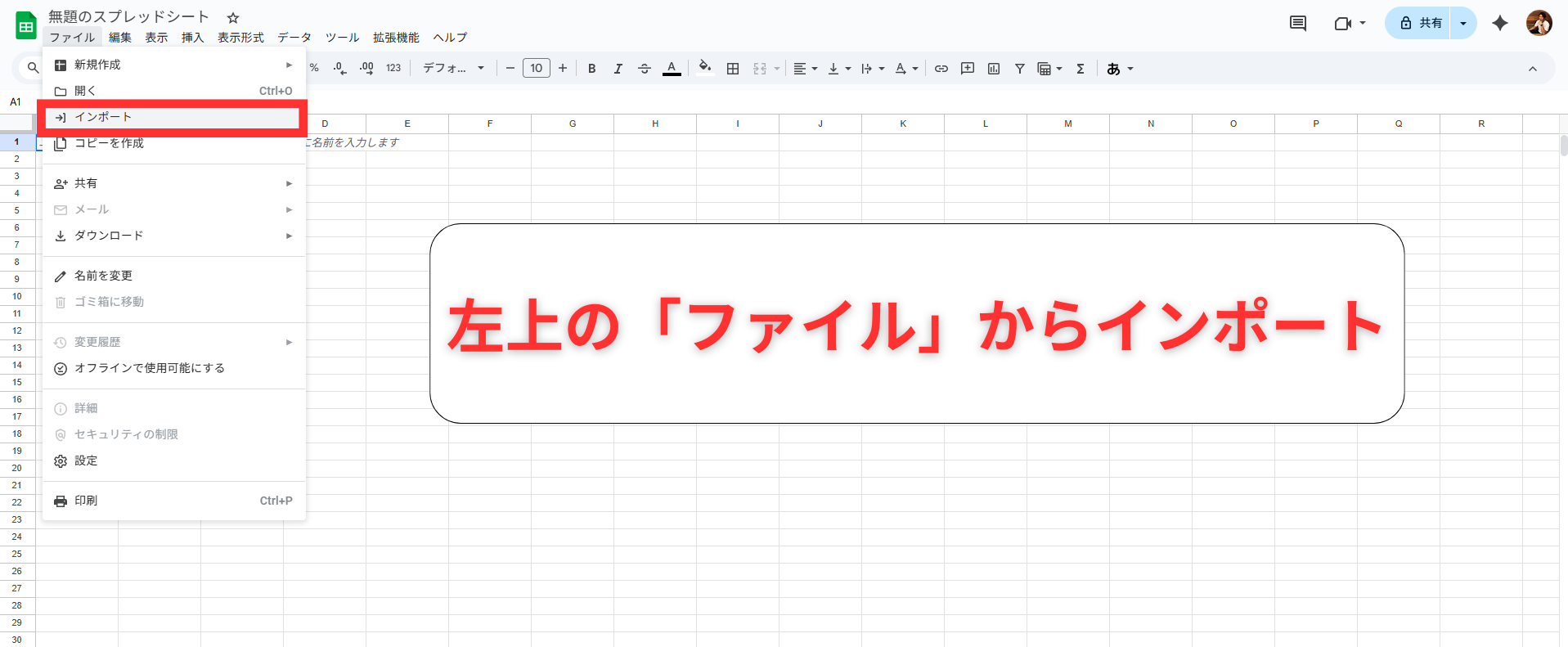
スプレッドシートを開き、
左上の「ファイル」から「インポート」を押し、
先ほどダウンロードしたファイルをアップロードする。
ステップ④
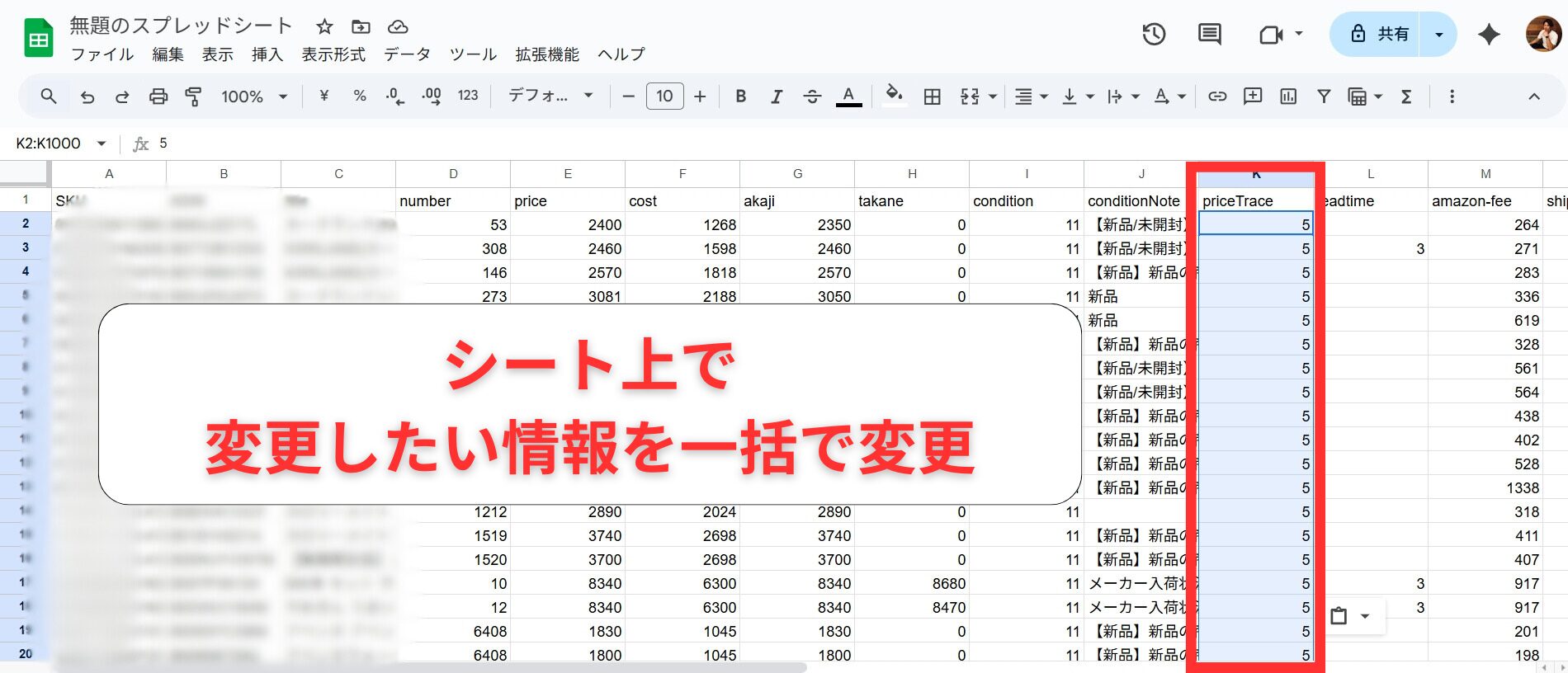
シート上で、変更したい情報を一括で変更していく。
一括で価格改定をしたい場合は、「price Trace」の欄の数字を変更するようにしましょう。
各条件の対応番号はコチラ👇

FBA状態合わせ:1
状態合わせ:2
FBA最安値:3
最安値:4
カート:5
※ちなみに、「akaji」の項目の数字が売値と同じ場合、赤字ストッパーがかかっている商品になるので、「akaji」の数字を売値より少し下げることをオススメします。
ステップ➄
で-修正後のファイルをダウンロード.jpg)
各情報の一括変更が終了したら、
左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式(,csv)」を押して、情報修正後のファイルをダウンロードする。
ステップ⑥
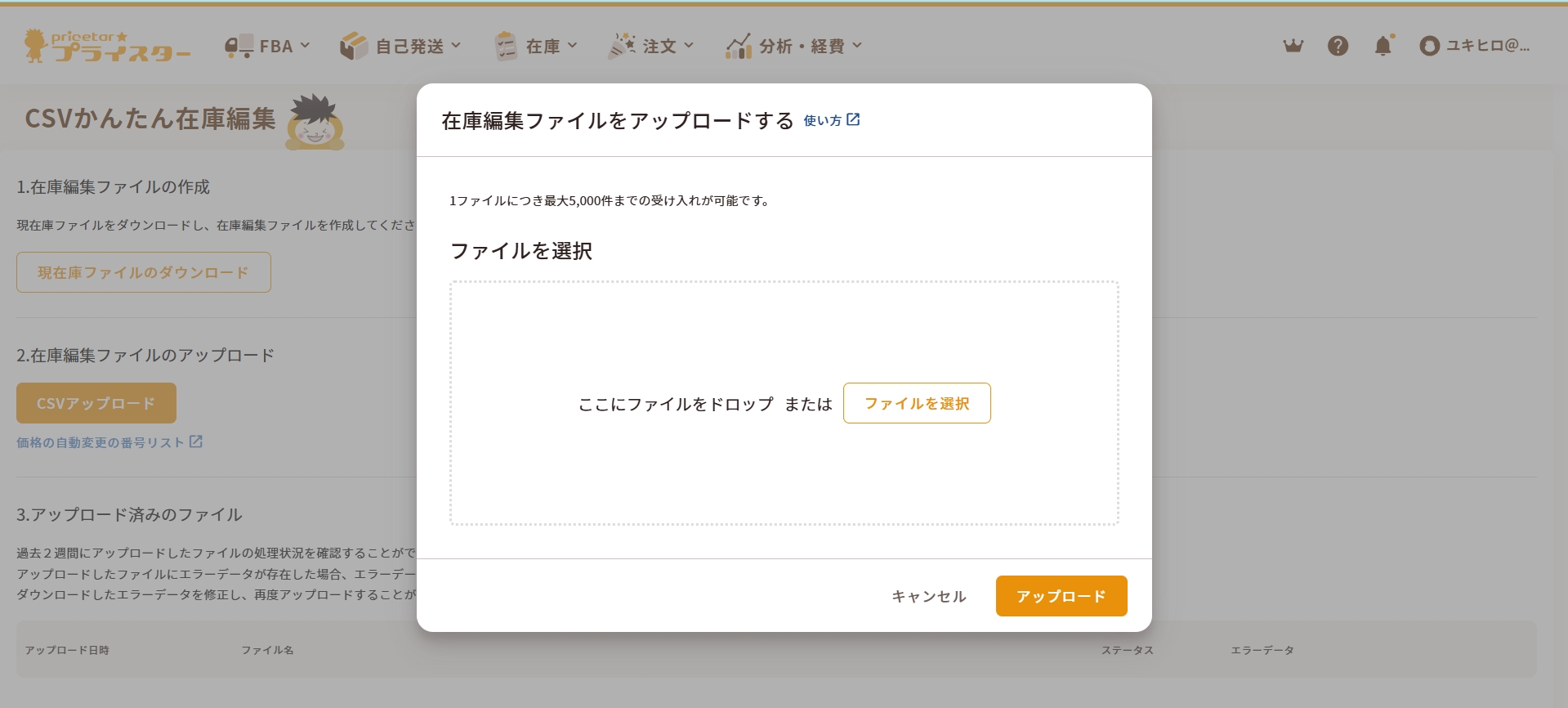
プライスターの画面に戻り、「CSVアップロード」から先ほどのファイルをアップロードする。
これで、一括変更は完了です!
初めてユキヒロを知った方へ
僕は個人事業主や小規模事業者向けに、
「メーカー問屋を軸とした物販を教える事業」を展開していて、
感覚や根性ではなく、誰でも再現できる「ロジカルな仕入れスキーム」の構築を得意としています!
これまでに、
✅自社で累計売上65億円以上達成 ✅メーカー問屋を始めて たった3年で年商15億 ✅大手メーカー12社、 問屋100社以上を開拓 ✅これまでに300名以上を指導 ✅教え子の月商1000万越え 40名以上、 ✅3000万越え15名以上輩出、 ✅月商100~500万 無数! ✅法人の顧問契約も累計16社以上
など、現場を通じてノウハウを磨いてきました!
今では胸を張れる会社に成長!
メーカー問屋仕入れを始めたい、伸ばしたい方へ
ここ数年で「メーカー・問屋仕入れ」を始める方は本当に増えています。
ですが、
実はそのほとんどの方が、
「毎日頑張ってるのに、思うように利益が残らない…」
という壁にぶつかっているのが現状。
情報発信を約7年、そして累計で300人以上の方にコンサルとして教えてきましたが、
多くの方が陥る課題はこれです👇
-
明確な基準がないまま、手当たり次第に営業
-
大量のメールや架電で消耗
-
実績作りや関係構築のために、ほぼ利益ゼロで購入
-
利益が出る前に心が折れ、リピートできず終了
-
薄利多売だから納品などを外注出来ずに消耗
僕自身も最初はこういった壁に多数ぶち当たってきました。
そして今回、メーカー問屋歴6年以上、累計売上65.1億円超売り上げてきた中で、
メーカー問屋仕入れの最適解を見つけました。
これだけ経験してきた中で、間違いなくこれが最適解だと確信できています。
とはいえ、
状況やステージによって最適なアプローチは異なります。
そこで、
個別壁打ち相談を受付中です(無料)
✅壁打ち相談会でできること
・あなたの状況・スキルに合わせた進め方の提案
・販路や仕入れルートの最適化アドバイス
・「これなら続けられる」設計づくり
🎯こんな方におすすめ
✅せどりである程度稼いで、
次にメーカー問屋を検討している
✅クリーンに物販を事業として育てたい
✅メーカー問屋に取り組んでいるが、
今ひとつ伸び悩んでいる
僕自身も昔は、
見積もりは取れても全然利益が出なかったり、
利益商品を見つけてもそれが続かなかったりと、
何度も壁にぶつかってきました。
だから今回、
あの頃の自分と同じように悩んでいる方の力になりたくて、
真面目に物販に向き合っている方限定で受付することにしました😊
▼ご相談の流れ ①現状をヒアリング ②あなたに合った改善策を一緒に整理 ③やるべきことが明確になる
僕の経験から、年商10憶規模までの方なら力になれると思います👍